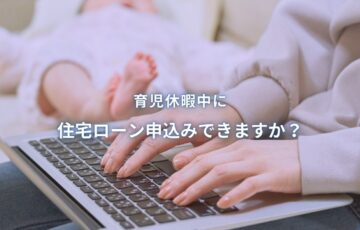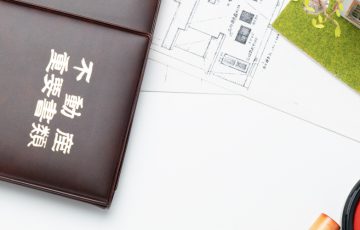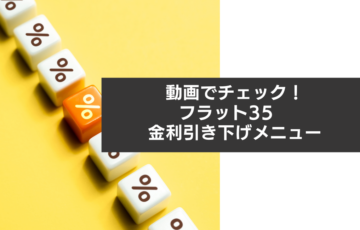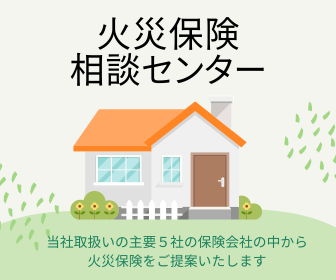2つの返済方法の違い
住宅ローンの返済方法には「元利均等返済」と「元金均等返済」があります。
「元利」均等返済方法は、毎月の返済額を一定にする方法です。返済当初は元金部分が少なく利息部分の返済比率が大きくなります。
一方「元金」均等返済方法は、毎月の返済額のうち元金部分を一定とする返済方法です。返済当初は元金に上乗せされる利息の支払いが大きくなります。
元利均等返済について
メリットは、毎月の返済額(元金+利息)が一定のため、返済計画を立てやすくなります。元金均等返済に比べて返済当初の返済額が少なく済みます。
デメリットは、同じ借入期間の場合、元金均等返済に比べて総返済額が多くなります。借入金残高の減り方が遅くなります。
元金均等返済について
メリットは、毎月の返済額(元金+利息)は返済が進むにつれて少なくなっていきます。元利均等返済に比べて元金の減少が早いため、同じ借入期間の場合、総返済額は少なくなります。
デメリットは、返済開始当初の毎月返済額が一番大きくなります。そのため借入時に求められる必要な年収も高くなります。
元利均等返済と元金均等返済の比較
元利均等返済の場合
【事例】
借入額:2000万円
固定金利:年1.2%
借入期間:35年
| 元利均等 | 毎月返済額 | 元金部分 (元金の割合) |
利息部分 (利息の割合) |
借入金残高 |
|---|---|---|---|---|
| 1年目 (12回目) |
58,340円 | 38,764円 (66.4%) |
19,576円 (33.6%) |
19,537,375円 |
| 5年目 (60回目) |
58,340円 | 40,669円 (69.7%) |
17,671円 (30.3%) |
17,630,374円 |
| 10年目 (120回目) |
58,340円 | 43,183円 (74.0%) |
15,157円 (26.0%) |
15,114,297円 |
| 15年目 (180回目) |
58,340円 | 45,852円 (78.6%) |
12,488円 (21.4%) |
12,442,716円 |
| 20年目 (240回目) |
58,340円 | 48,686円 (83.5%) |
9,654円 (16.5%) |
9,606,014円 |
| 25年目 (300回目) |
58,340円 | 51,695円 (88.6%) |
6,645円 (11.4%) |
6,593,988円 |
| 30年目 (360回目) |
58,340円 | 54,890円 (94.1%) |
3,450円 (5.9%) |
3,395,809円 |
| 合計(A) | 24,502,766円 | 20,000,000円 |
4,502,766円 |
– |
元金均等返済の場合
【事例】
借入額:2000万円
固定金利:年1.2%
借入期間:35年
| 元金均等 | 毎月返済額 | 元金部分 (元金の割合) |
利息部分 (利息の割合) |
借入金残高 |
|---|---|---|---|---|
| 1年目 (12回目) |
67,095円 | 47,619円 (71.0%) |
19,476円 (29.0%) |
19,428,572円 |
| 5年目 (60回目) |
64,809円 | 47,619円 (73.4%) |
17,190円 (26.6%) |
17,142,860円 |
| 10年目 (120回目) |
61,952円 | 47,619円 (74.0%) |
14,333円 (23.1%) |
14,285,720円 |
| 15年目 (180回目) |
59,095円 | 47,619円 (78.6%) |
11,476円 (19.4%) |
11,428,580円 |
| 20年目 (240回目) |
58,340円 | 47,619円 (84.7%) |
8,619円 (15.3%) |
8,571,440円 |
| 25年目 (300回目) |
53,380円 | 47,619円 (89.2%) |
5,761円 (10.8%) |
5,714,300円 |
| 30年目 (360回目) |
50,523円 | 47,619円 (94.3%) |
2,904円 (5.7%) |
2,857,160円 |
| 合計(B) | 24,209,800円 | 20,000,000円 | 4,209,800円 | – |
合計(A)-合計(B)=292,966円 となります。
元利均等返済よりも元金均等返済の方が総返済額は少なくなります。
元利均等と元金均等どちらを選ぶといいの?
上記のように返済方法の違いにより総返済額に差がでます。比較表では1.2%の固定金利を前提として計算をしており、35年間の総額で約29万円の差になります。
もし、前提として2%の固定金利で両方の総返済額の差を比較すると35年間で約81万円となります。借入金利が高い場合については元金均等を選択するメリットがより大きいと言えます。
しかしながら、現在のように低金利情勢にある場合は総返済額の差についてあまり気にせず、当初返済額が抑えられる元利均等返済を選択した方が良いと言えます。
ライフプランを考えた場合にも、住宅ローンを返済しながら子供の学資金を貯める必要等あるため、ゆとりを持った返済プランを選択しておいた方がよさそうです。
借入可能額の違い
元利均等返済と元金均等返済の借入可能額を計算してみます。
長期固定金利住宅ローンの「フラット35」では年収に応じた借入の返済比率が決まっています。
【事例】
金利:1.2%
借入期間:35年
年収:400万円以上(返済比率35%)にて計算
| 毎月返済額 | 元利均等返済 | 元金均等返済 |
|---|---|---|
| 7万円 | 2,390万円 | 2,070万円 |
| 10万円 | 3,420万円 | 2,950万円 |
| 13万円 | 4,450万円 | 3,840万円 |
住宅ローンの毎月返済額を10万円で見込んでいた場合、元利均等返済では3,420万円借りられるところ、元金均等返済を選択すると2,950万円しか借りられません。その差額は470万円にもなります。
まとめ
住宅ローンの返済方法は、ここ数年の低金利の情勢も追い風となって「元利均等」返済を選択する人の方が圧倒的に多くなっています。
借入可能額の計算には有利に働き、その一方で毎月の返済は当初抑えられた一定額で固定するからです。特に子育て世帯で、近い将来学費がかさむ家庭にとっては「元利均等」の方が有難いと思います。
また、住宅ローンの毎月返済額にゆとりを持たせるため「元利均等」返済を選択し、別途自身で積み立てして行って、子育てが終わったときに繰上げ返済をするのも非常に有効な手段です。
「元金均等」返済は、事業資金を借り入れた場合などに多い返済方法です。住宅ローンの返済においても元本を早く減らす方法のため総返済金額も元利均等返済より少なく済みますが、一方で返済当初の毎月返済額が大きくなります。また、そもそも金融機関によっては元金返済方法という選択肢がない場合もあります。
家計に十分ゆとりがある世帯や、夫婦のみの世帯、子育てが終わった世帯で、当初返済額が大きくても住宅ローンを少しでも早く返済したいと考える場合はこの返済方法が向いていると思います。